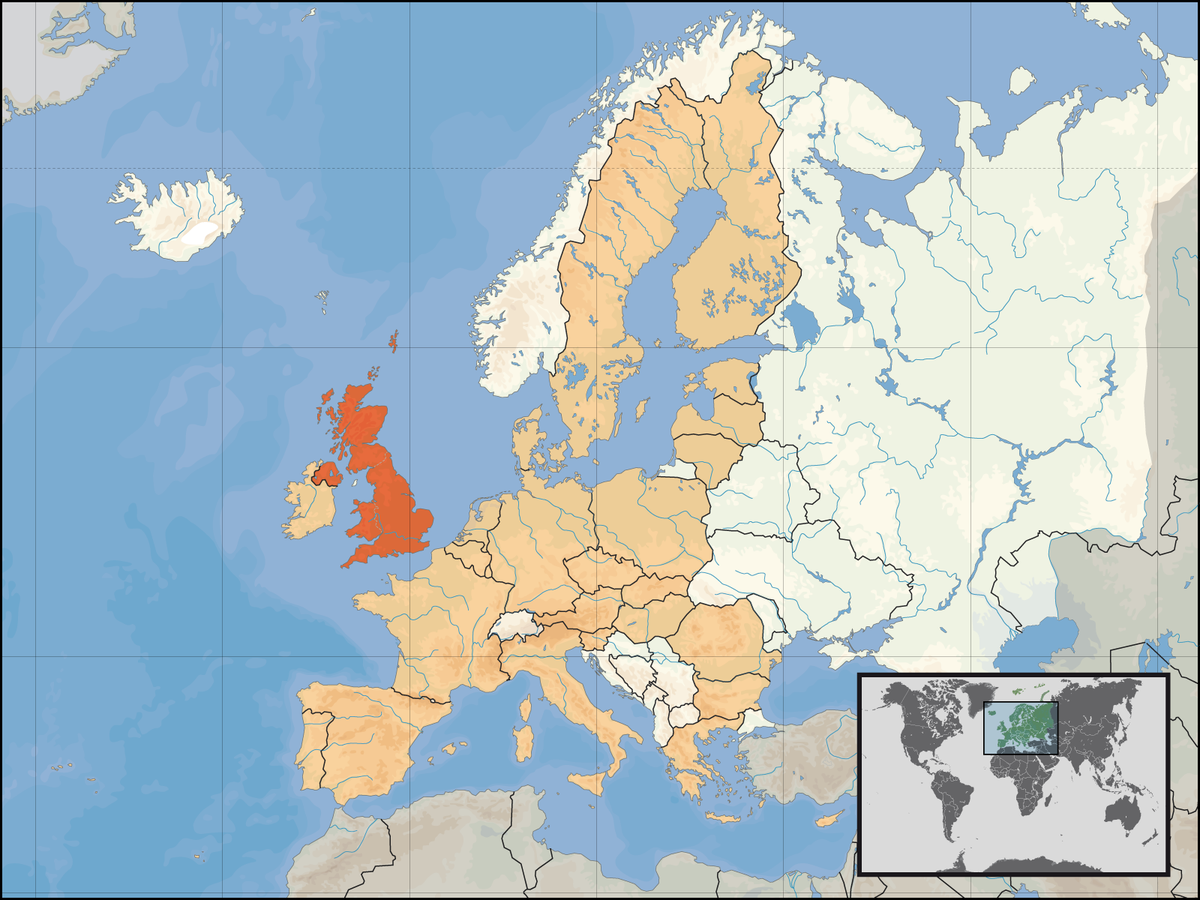1978年に発表された、U.K.の2枚目。
前作『U.K.』に比べて、ずいぶん大衆的というか、ケレン味のないというか、地味なアルバムであるが、佳作ではある。
前作『U.K.』に比べて、ずいぶん大衆的というか、ケレン味のないというか、地味なアルバムであるが、佳作ではある。
ドラムがビル・ブルーフォードに変わってテリー・ボジオ。
そしてギターのアラン・ホールズワースも脱退して、本来ジョン・ウェットンが構想していた3人組になった。
テリー・ボジオは、テクニシャンで鳴らしたビルブラの後任であるが、負けず劣らずのテクニックに加えて野獣的な力強さがある。
もともとフランク・ザッパ&マザーズにいてエディ・ジョブソンとは知り合いだった。
この人さいきんは日本の横須賀市に住んでいるそうだ。
そういえばカール・パーマーがぼくの故郷別府市の空手道場に通っているという噂もあるが、本当だろうか。
日本という国はプログレのドラマーに好まれるのかもしれない。
(2例だけだから・・・)
ボジオの話にもどるが、この人は野獣的なドラミングとはかけ離れた、ジャニーズ的な醤油顔のルックスをしている。
エディ・ジョブソンの組み合わせはルックス的に最強のプログレバンドと言えるのではないだろうか。
なお、ぼくは非常に評価が高いビルブラのドラムがあまり好きではない。
チューニングが異常に高い、カンカンというスネアがどうも耳につく。
U.K.の2枚目に戻る。
1曲目の「デンジャー・マネー」から、前作とは違って分かりやすいコード進行とメロディである。
キーボードがハモンドを中心なのも地味な印象を受ける。
歌詞も、前作はキング・クリムゾン的な狂気の世界を演出しようとして苦しんでいる印象を受けたが、このアルバムはぐっと分かりやすい。
「デンジャー・マネー」はスパイ小説というかハードボイルド的な世界である。
ちなみにジャケット・アートはピンク・フロイドのアルバムやユーミンの「昨晩お会いしましょう」で有名なデザイン工房ヒプノシスのナウい作品だが、たぶん1曲目のハードボイルドな歌詞からインスパイアされたものと思われる。
1作目が難解だったのでことさらに優しくしたというわけではなく、このアルバムあたりがジョン・ウェットンの本音だったのではないだろうか。
でもぼくには食い足りない気もする。
2曲目「ランデヴー6・02」もリリカルな、TOTOの「99」あたりを思わせるミディアム・テンポのバラード。
キーボードがエレピそのままなのもプログレではめずらしい感じがする。
ビデオは当時のMVだが、音楽に合わせてエア・バンドを行っている。
これ、U.K.のようなスーパーバンドでも(前作のアラン・ホールズワースでも)大まじめに演奏するふりをしているのがおかしい。
ジョン・ウェットンも当時やせててカッコよかったなー。
エディ・ジョブソンは器用な人で、どんな曲想でも合わせることが出来る。
なぜこの人が大スターにならないのか、不思議な気がするが、器用ナントカというやつかもしれない。
この曲は、途中の転調を繰り返す迷宮的なピアノソロがミステリアスな歌詞に合っていて素晴らしい。
この辺りからググッと聴く気が湧いてくる。
そして3曲目「The only thing she needs」が素晴らしい。
イエスの「ラウンドアバウト」、ディープ・パープルの「BURN(紫の炎)」、レッド・ツェッペリンの「アキレス最後の戦い」と並ぶ、ぼくが選ぶ「疾走感のあるブリティッシュ・ロック四天王」の1つである。
映像は2012年の再結成ライヴのモントリオール公演で、ファンが撮影したとおぼしい。
このメンバーで来日したのだが、この年は見逃している。
見ればよかった!
2012年になると、ジョン・ウェットンが超太っている。
グレッグ・レイクといい、なぜクリムゾンのベース&ヴォーカルの人って後でめちゃくちゃ太るのだろうか。
(2例だけだが)
それに対してボジオは、多少苦みばしってはいるが若々しいルックスを保っている。
のっけから野獣的なドラムソロ。
このドラムソロは日本の鈴木結女という人の曲にサンプリングして使われていた。
その後、本作にしては珍しいコテコテの変拍子のイントロ。
ハモンド丸出しのキーボードが逆にテクニックを見せつけてくれる感じでカッコいい。
歌詞は「あの女はワイルドだぜ」的な分かりやすいハードロックだ。
ところでこのアルバムから日本盤制作スタッフは無理矢理な邦題をやめて、英語題名をそのままカタカナ表記にすることにしたようだが、「ジ・オンリー・シング・シー・ニーズ」は邦題にした方がよかったのではないか。
中盤、ピアノのアルペジオに載せたドラムソロと、後半のヴァイオリン、ハモンドソロが盛り上がる。
ライヴ一発録りのようなハイ・テンションの曲である。
4曲目「Caeser's Pales Blues」はU.K.のメンバーが最も気に入っている曲なのではないだろうか。
いわゆるプログレ的な高級感、先進性と、ポップ性、疾走感が共存した曲だ。
音を聴いただけで、アクリル製の透明なヴァイオリンを得意げに弾いているジョブソンの姿が目に浮かぶ。
ちなみにこの透明なヴァイオリンは、ジャケット撮影用にはアクリルのムクのものを使っているが、実際に演奏するのは重すぎるので中空のものや、ワイヤーフレームのものを使っているそうだ。
5曲目「Nothing to lose」が問題作で、この曲で一気にU.K.から心が離れた。
超産業ロックで、わざとらしいほど分かりやすい。
U.K.のこの曲と、スーパートランプの「Breakfast in America」を聴いた時が、ぼくがプログレから心が離れた一瞬だったと思う。
シングルカットしたが、産業ロックとしてもなんかもの寂しい、スカッとしない曲で、こういう曲が売れると本気で思ってたとするとジョン・ウェットンはあまり商業的な才覚もなかったのではないか。
イエスの「ロンリー・ハート」とエライ違いである。
それにしても、この曲のビデオなどを見ると、ジョブソンとボジオは本当にアイドル的なルックスである。
ルックスだけ見るとベイ・シティ・ローラーズみたいである。
もうちょっとうまい売り方はあったんじゃないだろうかと今さら思う。
6曲目「Carrying No Cross」は、プログレ的な重々しさをなんとか出そうとした感じがする一曲である。
この曲もちょっと無理がある。
途中エディのアルペジエーターを使ったシンセソロのあとにピアノソロがあり、この作品ではめずらしいアトナールな感じになるが、これぐらいのソロならエディなら手クセそのままで弾けるのではないだろうか。
「In The Dead Of Night」のホールズワースのソロのような衝撃度はない。
このアルバムは2〜4曲目の3曲が、プログレ、ポップス、ハード・ロックの3要素が奇跡のバランスを保っていて素晴らしい。
しかしこういう曲は、それが素晴らしいと分かっていても作るのはなかなか難しいのだろう。
アルバム1枚目に比べると、魔術的な感じが息を潜めたアルバムである。
U.K.のスタジオアルバムはこの2枚目が最後となった。
それにしても3曲目、「The only thing she needs」は素晴らしい。
ロックの中のロック1曲である。
そしてギターのアラン・ホールズワースも脱退して、本来ジョン・ウェットンが構想していた3人組になった。
テリー・ボジオは、テクニシャンで鳴らしたビルブラの後任であるが、負けず劣らずのテクニックに加えて野獣的な力強さがある。
もともとフランク・ザッパ&マザーズにいてエディ・ジョブソンとは知り合いだった。
この人さいきんは日本の横須賀市に住んでいるそうだ。
そういえばカール・パーマーがぼくの故郷別府市の空手道場に通っているという噂もあるが、本当だろうか。
日本という国はプログレのドラマーに好まれるのかもしれない。
(2例だけだから・・・)
ボジオの話にもどるが、この人は野獣的なドラミングとはかけ離れた、ジャニーズ的な醤油顔のルックスをしている。
エディ・ジョブソンの組み合わせはルックス的に最強のプログレバンドと言えるのではないだろうか。
なお、ぼくは非常に評価が高いビルブラのドラムがあまり好きではない。
チューニングが異常に高い、カンカンというスネアがどうも耳につく。
U.K.の2枚目に戻る。
1曲目の「デンジャー・マネー」から、前作とは違って分かりやすいコード進行とメロディである。
キーボードがハモンドを中心なのも地味な印象を受ける。
歌詞も、前作はキング・クリムゾン的な狂気の世界を演出しようとして苦しんでいる印象を受けたが、このアルバムはぐっと分かりやすい。
「デンジャー・マネー」はスパイ小説というかハードボイルド的な世界である。
ちなみにジャケット・アートはピンク・フロイドのアルバムやユーミンの「昨晩お会いしましょう」で有名なデザイン工房ヒプノシスのナウい作品だが、たぶん1曲目のハードボイルドな歌詞からインスパイアされたものと思われる。
1作目が難解だったのでことさらに優しくしたというわけではなく、このアルバムあたりがジョン・ウェットンの本音だったのではないだろうか。
でもぼくには食い足りない気もする。
2曲目「ランデヴー6・02」もリリカルな、TOTOの「99」あたりを思わせるミディアム・テンポのバラード。
キーボードがエレピそのままなのもプログレではめずらしい感じがする。
ビデオは当時のMVだが、音楽に合わせてエア・バンドを行っている。
これ、U.K.のようなスーパーバンドでも(前作のアラン・ホールズワースでも)大まじめに演奏するふりをしているのがおかしい。
ジョン・ウェットンも当時やせててカッコよかったなー。
エディ・ジョブソンは器用な人で、どんな曲想でも合わせることが出来る。
なぜこの人が大スターにならないのか、不思議な気がするが、器用ナントカというやつかもしれない。
この曲は、途中の転調を繰り返す迷宮的なピアノソロがミステリアスな歌詞に合っていて素晴らしい。
この辺りからググッと聴く気が湧いてくる。
そして3曲目「The only thing she needs」が素晴らしい。
イエスの「ラウンドアバウト」、ディープ・パープルの「BURN(紫の炎)」、レッド・ツェッペリンの「アキレス最後の戦い」と並ぶ、ぼくが選ぶ「疾走感のあるブリティッシュ・ロック四天王」の1つである。
映像は2012年の再結成ライヴのモントリオール公演で、ファンが撮影したとおぼしい。
このメンバーで来日したのだが、この年は見逃している。
見ればよかった!
2012年になると、ジョン・ウェットンが超太っている。
グレッグ・レイクといい、なぜクリムゾンのベース&ヴォーカルの人って後でめちゃくちゃ太るのだろうか。
(2例だけだが)
それに対してボジオは、多少苦みばしってはいるが若々しいルックスを保っている。
のっけから野獣的なドラムソロ。
このドラムソロは日本の鈴木結女という人の曲にサンプリングして使われていた。
その後、本作にしては珍しいコテコテの変拍子のイントロ。
ハモンド丸出しのキーボードが逆にテクニックを見せつけてくれる感じでカッコいい。
歌詞は「あの女はワイルドだぜ」的な分かりやすいハードロックだ。
ところでこのアルバムから日本盤制作スタッフは無理矢理な邦題をやめて、英語題名をそのままカタカナ表記にすることにしたようだが、「ジ・オンリー・シング・シー・ニーズ」は邦題にした方がよかったのではないか。
中盤、ピアノのアルペジオに載せたドラムソロと、後半のヴァイオリン、ハモンドソロが盛り上がる。
ライヴ一発録りのようなハイ・テンションの曲である。
4曲目「Caeser's Pales Blues」はU.K.のメンバーが最も気に入っている曲なのではないだろうか。
いわゆるプログレ的な高級感、先進性と、ポップ性、疾走感が共存した曲だ。
音を聴いただけで、アクリル製の透明なヴァイオリンを得意げに弾いているジョブソンの姿が目に浮かぶ。
ちなみにこの透明なヴァイオリンは、ジャケット撮影用にはアクリルのムクのものを使っているが、実際に演奏するのは重すぎるので中空のものや、ワイヤーフレームのものを使っているそうだ。
5曲目「Nothing to lose」が問題作で、この曲で一気にU.K.から心が離れた。
超産業ロックで、わざとらしいほど分かりやすい。
U.K.のこの曲と、スーパートランプの「Breakfast in America」を聴いた時が、ぼくがプログレから心が離れた一瞬だったと思う。
シングルカットしたが、産業ロックとしてもなんかもの寂しい、スカッとしない曲で、こういう曲が売れると本気で思ってたとするとジョン・ウェットンはあまり商業的な才覚もなかったのではないか。
イエスの「ロンリー・ハート」とエライ違いである。
それにしても、この曲のビデオなどを見ると、ジョブソンとボジオは本当にアイドル的なルックスである。
ルックスだけ見るとベイ・シティ・ローラーズみたいである。
もうちょっとうまい売り方はあったんじゃないだろうかと今さら思う。
6曲目「Carrying No Cross」は、プログレ的な重々しさをなんとか出そうとした感じがする一曲である。
この曲もちょっと無理がある。
途中エディのアルペジエーターを使ったシンセソロのあとにピアノソロがあり、この作品ではめずらしいアトナールな感じになるが、これぐらいのソロならエディなら手クセそのままで弾けるのではないだろうか。
「In The Dead Of Night」のホールズワースのソロのような衝撃度はない。
このアルバムは2〜4曲目の3曲が、プログレ、ポップス、ハード・ロックの3要素が奇跡のバランスを保っていて素晴らしい。
しかしこういう曲は、それが素晴らしいと分かっていても作るのはなかなか難しいのだろう。
アルバム1枚目に比べると、魔術的な感じが息を潜めたアルバムである。
U.K.のスタジオアルバムはこの2枚目が最後となった。
それにしても3曲目、「The only thing she needs」は素晴らしい。
ロックの中のロック1曲である。
 イジハピ!
イジハピ!